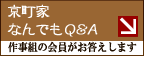俳句の研究や創作をする過程で、常に頭の中に巡るのは芭蕉の句である。 名月や池をめぐりて夜もすがら
芭蕉が、この地で本当に月を見たのか、ひと晩中、池を巡ったのか等、事実か否かは問題ではないであろう。 そのような設定で、秋の季語である名月を詠み込んだこと、そして、広沢池の池畔に句碑があることによって、芭蕉の句のイメージがより鮮明に現代にまで通じているという事実こそが、意義のあることと思われる。 作者が「月」や「池」という「物」をどのように捉え、どのような状況設定をするかによって、俳句という言語芸術作品が完成する。池を「巡る」という行為、その行為がひと晩中続いたという設定、その行為は、名月の素晴らしさからきたものであるという感動を強める切れ字「や」など、心と言葉の様々な趣向の要素が巧みに絡み合い、芸術性を帯びてゆく。 作者自身が、ひとつひとつの言語にこだわりをもって、より良い作品を創作したいと切望するからこそ、心に残る芸術作品が生まれるのである。そのような「こだわり」は、俳句などの言語芸術のみではなく、全ての芸術に存在する。 芭蕉が生涯に詠んだ句、約千句の中で、秋の月を詠み込んだ句は、八十句ほど。約8%にあたる。 寛文3年(1663)に詠んだ 月ぞしるべこなたへ入らせ旅の宿 から始まり、様々な秋の月が芭蕉という芸術家によって表現されている。 元禄2年(1689)芭蕉46歳の時、『奥の細道』の旅に出る。有名な冒頭部分で、「先ず松島の月心にかかりて」と、松島への想い、月の松島の光景への想いを述べる。果たして到着した松島では、絶景に心を奪われ、句が作れなかったと記している。しかし、それもひとつのパフォーマンス。そのような設定で文章(俳文)を創っているのである。 いかなる芸術も、良い意味で、虚構の世界を楽しむものであり、完成した作品の事実を追求するためのものではない。 『奥の細道』の他のシーンでは、一振(新潟県)の宿の景が詠まれる。 一家に遊女も寝たり萩と月 また、北国の天候の変わり易さを「名月」とともに表現した句もある。 名月や北国日和定なき
三井寺の門たたかばやけふの月 鎖あけて月さし入れよ浮御堂 いずれも、ドラマチックで、絵画的な趣向が詠まれるが、特に、「月さし入れよ」との表現に至る発想は、殊更に魅了される。 門人の若妻のもてなしに芭蕉が感心して詠んだ句がある。 月さびよ明智が妻の咄しせん 明智光秀の妻は、自分の長い髪を切り売って、困窮を救った良妻として知られる。その話を門人夫妻に語ろうというのである。 「もてなし」という行為に対して「俳句」という芸術で返す、最高級の芸術家、芭蕉の詩心が存分に発揮された作品である。 明智光秀は、本能寺の変で織田信長を撃つ前に、京都の愛宕山に向かい、愛宕神社で連歌を詠んだ。そのような事も交えながら、秋の月の下で、しみじみと語り合ったのかも知れない。 秋の季語「月」の句をめぐって、芭蕉の芸術の世界に触れ、少しでも芭蕉の境地へ近づきたいと思うのは、多くの芸術家(詩人)としての果てしなき夢である。 |
|||
(2008.9.1) |
|||
|