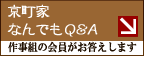あれは、二年前の春でした。『京町家友の会』の歳時記で催された「お花見」のひととき…。美しい小雨模様の中、木屋町から団栗橋を渡り、祇園から石塀小路を抜け、八坂神社、円山公園に向けて進みました。萬次郎でお茶をいただいて解散した後、夕刻を待って青蓮院の拝観や祇園白川の夜桜とのご対面。翌日は好天に恵まれ、御所から鴨川堤、平安神宮や疎水の岸辺など、たくさんの桜を愛でるうちに…、なんとも贅沢なことに“花疲れ”を覚えました。そこで鞍馬から貴船までの緑深き逍遥路で目を休め、再び下鴨神社から鴨川の堤へ。桜、さくら…。“桜尽くし”の二日間でした。 私のお気に入りは「枝垂れ桜」。これは「江戸彼岸」から生まれた“ミュータント”です。したがって、葉に先立って花が咲くこと、花の付け根(萼)の基部がビーズ玉の ように丸いこと、蕾の時にめしべの先がはみ出して見えることなど、江戸彼岸の特徴が受け継がれています。古来より、枝垂れるのは精霊が宿るからだとされ、寺社などにも多く植えられました。近年、日本女子大学理学部の中村輝子博士はそのメカニズムを植物生理学的に解明しています。博士のご研究を私なりに要約すれば、“生長ホルモン”の一種であるジベレリンの生成濃度がアンバランスなため、枝が固まるより早く伸びてしまい、自からの重さで枝垂れるのだそうです。
早春に一足早いお花見を楽しませてくれるのは「寒桜」。これは山桜と「寒緋桜(かんひざくら)」との交雑種です。寒緋桜は早咲きで、うつむき加減に半開きの花形と濃い花色が特徴。もとの呼び名は緋寒桜(ひかんざくら)でしたが、「彼岸桜」との混同を避けるために改名されました。標準和名をカタカナで表記して、口頭で発表する学会では「カ・ガ」の混同は、研究の成果を台無しにするからです。ただし、新聞などの開花ニュースには“現地・原音主義”により、緋寒桜の名も使われます。一般に寒緋桜の交雑種はどれも早咲きが得意です。近年話題の「河津桜」もその一つです。  さて、東京の桜といえば「染井吉野」でしょうか。明治維新の前夜に江戸の染井村(今日の豊島区)に出現したニューフェイス。はじめは吉野桜などと呼ばれましたが、明治33年(1900)に藤野寄命博士によって正式に命名されました。江戸彼岸(花粉)と「大島桜」(雌しべ)の交雑種といわれますが、実際に掛け合わせると…、すべてが染井吉野になるのではありません。また、交雑実験によって生まれた「天城吉野」や「伊豆吉野」などに白い花が咲くのは、大島桜の性質を強く受け継いだからでしょう。一方、毎年開催される『日本さくらの会』の研究発表会のご常連である、育種家の白井勲さんは、どのような花色の桜でも自由に作り出すことが出来るそうです。そして全国的に染井吉野の花が白くなったことを憂い、“桜色”の花をもつ後継樹をご研究中です。
さて、東京の桜といえば「染井吉野」でしょうか。明治維新の前夜に江戸の染井村(今日の豊島区)に出現したニューフェイス。はじめは吉野桜などと呼ばれましたが、明治33年(1900)に藤野寄命博士によって正式に命名されました。江戸彼岸(花粉)と「大島桜」(雌しべ)の交雑種といわれますが、実際に掛け合わせると…、すべてが染井吉野になるのではありません。また、交雑実験によって生まれた「天城吉野」や「伊豆吉野」などに白い花が咲くのは、大島桜の性質を強く受け継いだからでしょう。一方、毎年開催される『日本さくらの会』の研究発表会のご常連である、育種家の白井勲さんは、どのような花色の桜でも自由に作り出すことが出来るそうです。そして全国的に染井吉野の花が白くなったことを憂い、“桜色”の花をもつ後継樹をご研究中です。おしまいに…、私の大好きな鴨川は“理想的”な都市河川です。情緒ある河畔の桜並木をはじめ、その風景のおおらかさ、子どもたちの歓声や、カップルの囁き、東山の連なりや鞍馬山方面への遠近景観…。そして何よりも、鴨川全体が巨大な帯状の“ビオトープ”として環境省の「生物多様性国家戦略」(勇ましい名前ですが)に貢献しているのです。そこには綺麗な水の流れがあり、そこに生きる水生昆虫や魚たちがいます。それらを餌にする小鳥や水鳥、川原の草むらに跳ねるバッタや、飛び交うトンボの群れ、たくさんの生きものたちと相互のつながり、また気象の緩和も…。こうしてみると、今日の鴨川が備えている貴重な“属性”と「京町家」のそれとの間には、大きな共通項があるように思えます。
(2006.3.1) |
||||||
|