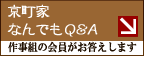現在日本の禅宗とは、曹洞宗、黄檗宗、臨済宗の三宗を指しますが、各宗の宗祖も成立年代も夫々異なり、歳時記には多少の差異があります。愚衲の属する大徳寺は、臨済宗大徳寺派の寺院で、中国唐代の臨済(りんざい)義(ぎ)玄(げん)禅師(?〜867年)が宗祖です。但し禅宗と云い臨済宗と呼べども仏教の一派であり、歳時記の眼目となるのは釈尊の忌日です。 即ち釈尊が入寂(にゅうじゃく)された二月十五日に涅槃図(ねはんず)を掛けて行われる涅槃会(ねはんえ)、釈尊の誕生日である四月八日に誕生仏に甘茶をかけて祝う降誕会(ごうたんえ)、釈尊がお悟りを開かれた十二月八日に行われる成道会(じょうどうえ)のいわゆる三仏忌は全国の仏教寺院で法要が営まれます。加えて禅宗の始祖達磨(だるま)大師(だいし)(5世紀末〜6世紀始)と百丈(ひゃくじょう)禅師(ぜんじ)(749年〜814年、禅寺の規則の基を作った中国唐代の禅僧)の二祖の忌日が、二祖三仏忌(三仏二祖忌ともいう。二祖は禅宗内でも夫々異なる)と称して、年間の重要な行事であり、一宗の宗祖や一寺の開山、一院、一庵の開祖や開基の忌日も同じく大切に考えられています。一般的には歳晩、正月行事、節分、春秋のお彼岸、並びに七月又は八月のお盆の行事が有名ですが、ここでは触れません。  禅寺の歳時記で重要とされ、且つ特徴的なものは、安居(あんご)です。安居(あんご)は、雨期を意味するサンスクリット語の意訳で、雨(う)安居(あんご)の略。別に夏(げ)行(ぎょう)、座(ざ)夏(げ)、夏書(げしょ)、夏(げ)経(きょう)、夏断(げだん)、または単に夏(げ)と言う。「安」は心身を静止の状態にすること、「居」は一所に定住して動かないことです。釈尊在世の頃からインドの雨期三月間は、移動も困難で教化活動も難しく、かつこの時期に発生する虫や草木を殺傷しないために、一箇所に集合して禁足し座禅修学を専らにする制が設けられた。三ヶ月即ち九旬の期間中、制を結ぶので、一夏九(いちげく)旬(じゅん)、九旬禁足、結制(けっせい)安居(あんご)などと称する。後に中国に於いては気候風土の違いから、夏(雨)と冬(雪)の二安居(あんご)が一般的となった。現在の日本に於いても全国の専門道場即ち僧堂で、四月十五日又は五月一日から、七月十五日又は七月三十一日までの雨(う)安居(あんご)と、十月十五日又は十一月一日から翌年の一月十五日、二月一日又は二月十五日までの雪(せつ)安居(あんご)の年間二安居制が行われている。 禅寺の歳時記で重要とされ、且つ特徴的なものは、安居(あんご)です。安居(あんご)は、雨期を意味するサンスクリット語の意訳で、雨(う)安居(あんご)の略。別に夏(げ)行(ぎょう)、座(ざ)夏(げ)、夏書(げしょ)、夏(げ)経(きょう)、夏断(げだん)、または単に夏(げ)と言う。「安」は心身を静止の状態にすること、「居」は一所に定住して動かないことです。釈尊在世の頃からインドの雨期三月間は、移動も困難で教化活動も難しく、かつこの時期に発生する虫や草木を殺傷しないために、一箇所に集合して禁足し座禅修学を専らにする制が設けられた。三ヶ月即ち九旬の期間中、制を結ぶので、一夏九(いちげく)旬(じゅん)、九旬禁足、結制(けっせい)安居(あんご)などと称する。後に中国に於いては気候風土の違いから、夏(雨)と冬(雪)の二安居(あんご)が一般的となった。現在の日本に於いても全国の専門道場即ち僧堂で、四月十五日又は五月一日から、七月十五日又は七月三十一日までの雨(う)安居(あんご)と、十月十五日又は十一月一日から翌年の一月十五日、二月一日又は二月十五日までの雪(せつ)安居(あんご)の年間二安居制が行われている。安居(あんご)の始まりを結(けつ)夏(げ)、結制(けっせい)または入制(にゅうせい)といい、安居(あんご)の終わりを解(かい)夏(げ)または解制(かいせい)という。安居(あんご)期間中は一週間単位で座禅三昧の日々を送る事となる。この一週間の座禅強調週間を攝(せっ)心(しん)(心を摂(おさ)めて、乱さないこと)と呼び、その厳しさの度合いによって小攝(こぜっ)心(しん)や大攝(だいせっ)心(しん)と呼ぶ。又、大攝心の前に一週間予備の小攝心を行う。これを地取攝(じどりせっ)心(しん)と云い、大攝心の後の小攝心を練返(ねりかえ)し攝心と呼んでいる。 大攝心には入(にゅう)制大攝(せいだいせっ)心(しん)(安居の始めの攝心)、半夏大攝(はんげだいせっ)心(しん)(安居の半ばの攝心)、夏(げ)末大攝(まつだいせっ)心(しん)(安居の終わりの攝心)及び臘八大攝(ろうはつだいせっ)心(しん)(十二月八日つまり臘月八日に釈尊が成道されたことに因んで、十二月一日より行われる最も厳しい攝心)があり、これを何年も繰り返して初めて住職となることが出来る。古くは十回安居を修さなければ和尚とは呼ばれなかった。現在は年間二安居を三年過ごし、都合六安居を修して初めて住職資格が与えられる(大徳寺派の場合)。無論これは修行中の話ではありますが、本山の塔頭(たっちゅう)寺院(本山の中にあって高僧の塔所(たっしょ)や、大名等の菩提寺である院や庵)の住職は、本山道場の入制や解制の行事には必ず参加する。その事によって現在は攝(せっ)心(しん)に参加していない和尚方も専門道場での辛く楽しい日々を思い起こすのです。 |
||
|