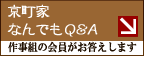年が明けると、お茶の世界では各所で初釜がかけられる。裏千家での「初釜式」の模様は毎年、テレビでも報じられ、おなじみの正月風景となっている。私の習っている先生のところでも、初釜があり、それに出向くことになる。 キリッと冷えた空気に身も心も引き締まる思いで門をくぐり、受け付けから待合に通される。待合では大きな火鉢に新しい藁灰が黒々と盛られ、その中心に炭が暖かな色をして我々を迎えてくれる。床にはおめでたい軸がかけられ、炭やきらびやかな香合が飾られてある。しばらくするとお湯が出て、茶席へと向かう。庭の敷き松葉が美しい。結界の新しい青竹や苔と対比して、すがすがしさの中に落着きを見せている。年が明けて何もかもが新しく整えられる中で、秋に落ちた枯れた松葉を集めて、洗い清めて路地や庭に敷く。苔などが霜で傷むのを防ぐ意味があると聞いたが、青々とした苔や青竹の、命あるもの、伸び行くもののイメージの上に枯れ色の松葉がそれを包み込み、守っているように見える。初めて見たときは、単に松葉が落ちているのだな、としか見えなかったが、見えてくるとそこに準備する人の思いが感じられるようになる。蹲(つくばい)には湯桶が用意されており、その湯で手水を使って席に入る。 本席の床の間には、正月を祝う言葉が書かれた軸がかけられ、天井から床にまで達する「結び柳」が飾られている。この席で小梅と結び昆布をいただき、暖かい皿に味噌あんを敷いた餅が出てくる。これをいただくと、先生のお点前で濃茶が出される。濃茶を点てるというのは、不思議なもので、ただお茶の粉を少量のお湯で練るだけなのだが、実際に稽古してみると、茶筅を通じてお茶が練られていく、非常に微妙な感触に感覚が集中して、荒いかたまりが、次第に細かいコロイド状になっていくのが感じられる。その中で、茶碗やお茶そのもの、それに注ぐお湯などと茶筅を通じて対話しているように思えてくる。さらにその後ろには、お茶を育てた太陽や土、雨や風といった自然、手をかけて育てた人々、加工した人々の思い、茶碗の元になった土、茶碗を作った人、水の良さやそれを湯にしている釜や炭があり、そんなところまで想いが及んでしまう。完璧に、世間の時の流れとは別の世界に入り込んで、一心にただただお茶を練ることで自分自身の魂が磨かれるような気がする。修練を積んだ職人の指先がミクロン単位の違いを感じるのと同じような世界がここにはある。こういった、普通の生活とは違った時間を過ごす瞬間があるのがお茶の魅力でもある。濃茶をいただくと、点心の席へと移る。 先ほどとは一変して、なごやかな場となる。塗(ぬり)の盃と共に先生がたがお酌に回って来られる。正月の挨拶をしてお酒をいただく。いつも思うのだが、こういう席でのお酒は本当においしい。何人も回って来られるので、結構お酒をいただくことになるがこれも修練(?)と思って素直にいただく(お茶事では「千鳥の盃」とかがあり、お酒を飲めないとお茶事の亭主は勤まらない)。食事が終わると、最後に薄茶が点てられる。お酒を飲まされて酔いの世界に一旦入ったと思ったら、またお茶をいただくことで現実世界に引き戻される。あの世とこの世を行ったり来たりしているようなところがある。そう思うとお茶というのは、どうも魂が自分の肉体から、ふっと離れるような感覚を目指しているように思われてくる。これはお茶の世界の隠れた本質ではないかと、ひそかに思っているところである。 外に出ると、お酒の入った後には、空気の冷たさが心地よい。初釜が終わると、京都の寒さもいよいよ本格的になってくる。 (再生研究会幹事) |
||
|